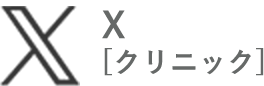亜鉛を摂りすぎるとはげるって本当?
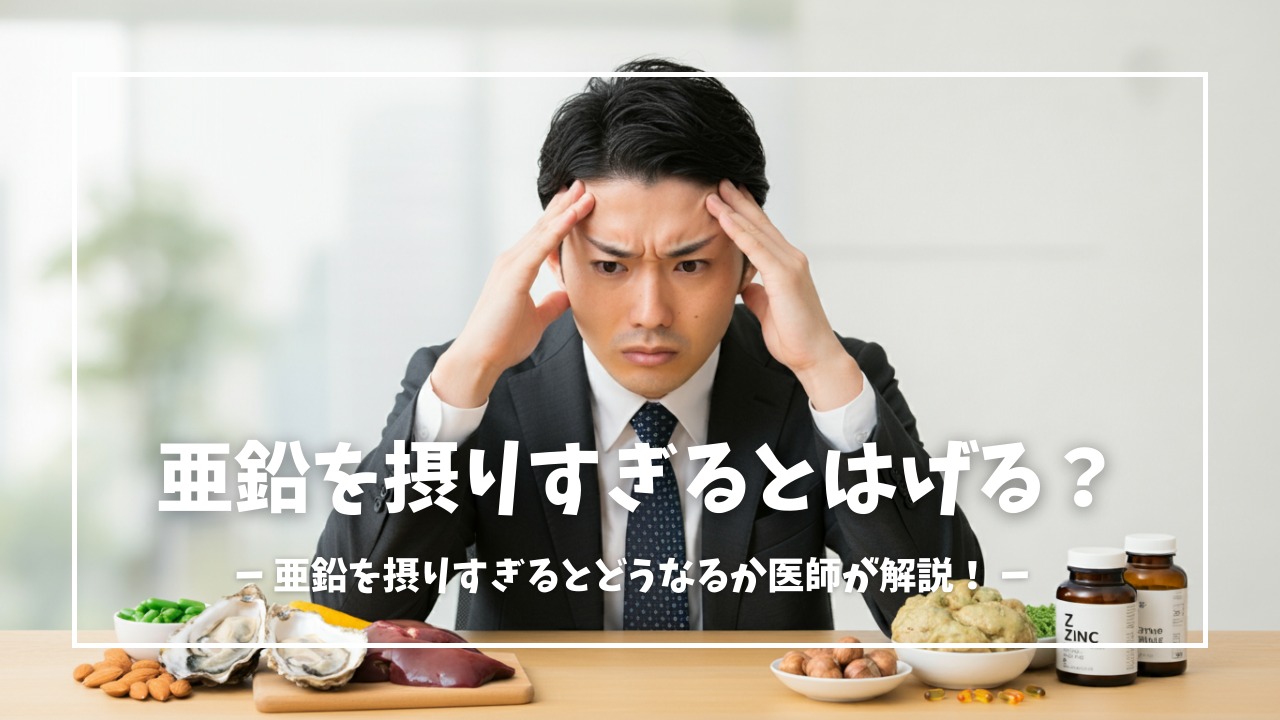
亜鉛は髪の毛によい栄養素として知られていますが、多く摂りすぎると逆に薄毛などを引き起こす可能性があるため注意が必要です。
この記事では、亜鉛が髪の毛に与える影響や過剰摂取が引き起こす可能性がある症状、推奨基準量、耐容上限量などについて解説します。
また、亜鉛が多く含まれている食材や亜鉛と一緒に摂取した方がよい食材なども紹介するので、薄毛や抜け毛でお悩みの方は、今後の参考にしてみてください。
もくじ
亜鉛が髪の毛に与える影響とは?
亜鉛は、必須ミネラルのひとつであり、体内で合成されないため食事など外部から摂取する必要があります。
亜鉛が髪の毛に与える影響は主に以下の3つです。
・髪の毛を生成する
・ヘアサイクルを正常に戻す
・AGA(男性型脱毛症)の進行を抑制する
それぞれについて詳しく解説していきます。
髪の毛を生成する
摂取したタンパク質は体内でアミノ酸に分解されてから吸収され、髪の毛の主成分であるケラチンへ再合成されます。
亜鉛は、ケラチンを再合成するときに必要な栄養素です。
そのため、適切な量の亜鉛を摂取すると髪の毛の生成をサポートし、薄毛や抜け毛の改善が期待できると考えられています。
ヘアサイクルを正常に戻す
ヘアサイクルとは、髪の毛が生えて成長し抜け落ちるまでの周期のことを指します。
ヘアサイクルは、成長期と退行期、休止期の3つに分類されます。
成長期は毛母細胞が活発に細胞分裂をして髪の毛が成長する期間で、退行期は髪の毛の成長が止まり抜け落ちるまでの期間、休止期は髪の毛が抜け落ちて次の髪の毛が生えてくるまでの準備期間です。
ヘアサイクルが乱れて成長期が短くなると、太く抜けやすい髪の毛まで成長することができず、細く抜けやすい髪の毛が多くなり薄毛になってしまいます。
亜鉛は、毛母細胞が細胞分裂するために必要な栄養素で、適切な量を摂取するとヘアサイクルを正常に戻すように働くといわれています。
AGAの進行を抑制する
男性ホルモン(テストステロン)は、5α-リダクターゼという還元酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。
変換されたDHTは、毛乳頭細胞にある男性ホルモン受容体(アンドロゲンレセプター)と結合すると、退行期誘導因子(脱毛因子)であるTGF-βが産生され、毛髪の正常な成長が妨げられて、抜け毛が増えてしまうのです。
亜鉛は、5α-リダクターゼの働きを阻害する栄養素のため、AGAの進行を抑制することが期待されています。
亜鉛を摂りすぎるとはげるの?
亜鉛の摂りすぎが直接薄毛を引き起こすことはありません。
しかし、薄毛につながる症状を引き起こす可能性があります。
亜鉛を過剰摂取すると、髪の毛の成長に必要な他の栄養素が吸収されにくくなり、薄毛や抜け毛のリスクが高くなってしまうのです。
亜鉛は、髪の毛の成長に必要な栄養素ですが、適切な量を摂取するようにしましょう。
亜鉛の過剰摂取により起こる可能性がある症状
亜鉛を過剰摂取すると以下のような副作用を引き起こすことが知られています。
・貧血
・悪心
・免疫力の低下
・吐き気
・食欲不振
・下痢
・頭痛
また、亜鉛の過剰摂取は前立腺がんのリスクを高めるという報告もあります。
亜鉛の摂取量に気をつけ、バランスの取れた食事を取ることを心がけましょう。

亜鉛の推奨摂取量と耐容上限量
厚生労働省が作成した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、亜鉛の1日当たりの推奨摂取量と耐容上限量は以下の通りです。
耐容上限量とは、過剰摂取による健康被害を未然に防ぐ目安量をあらわしています。
| 対象 | 食事摂取基準量 | 耐容上限量 |
|---|---|---|
| 成人男性 | 11mg/日 | 40~45mg/日 |
| 成人女性 | 8mg/日 | 30~35mg/日 |
| 妊婦 | 11mg/日 | – |
| 授乳婦 | 12mg/日 | – |
※耐容上限量は、過剰摂取による健康リスクを避けるための目安です。
男性の方が女性よりも食事摂取基準量も耐容上限量も少し高いですが、それほど大きな差はありません。
耐容上限量は、食事摂取基準量の4倍前後です。
サプリメントを飲むときは、亜鉛の含有量を確認して、摂取しすぎないように注意してください。
亜鉛が多く含まれているおすすめの食材
亜鉛は、魚介類や肉類、野菜、豆類などさまざまな食材に含まれていますが、効率良く摂取したい方は、亜鉛が多く含まれている食材を食べることをおすすめします。
文部科学省が作成している「食品成分データベース」から、亜鉛が多く含まれている食べ物の中から食事として摂取しやすい食材を選び以下の表にまとめました。
| 食材名 | 食材100g当たりに含まれる亜鉛量 |
|---|---|
| 牡蠣(生) | 14.0mg |
| スモークレバー(豚) | 8.7mg |
| かたくちいわし(田作り) | 7.9mg |
| かぼちゃ(いり、味付け) | 7.7mg |
| まいたけ(生) | 6.9mg |
| 豚レバー(生) | 6.9mg |
| 牛もも肉(皮下脂肪なし、焼き) | 6.3mg |
| 牛ヒレ肉(赤肉、焼き) | 6.0mg |
| 鶏卵(ゆで) | 3.3mg |
| うなぎ(かば焼き) | 2.7mg |
| 切り干しだいこん(乾) | 2.1mg |
牡蠣は、他の食材に比べると非常に多くの亜鉛が含まれています。
牡蠣の他には牛肉やまいたけ、かぼちゃなどにも多くの亜鉛が含まれているため、亜鉛を効率良く摂取したい方にはおすすめの食材です。
食事だけで亜鉛の過剰摂取は難しい
普通に食事を取っている人は、亜鉛の過剰摂取は起こりにくいです。
最も亜鉛が含まれている牡蠣でも100g当たり14mgしか含まれていません。
平均的な大きさの牡蠣1個の重さは20g程度です。
成人男性の牡蠣の耐容上限量は40〜45mgで、牡蠣では300g前後になります。
牡蠣300gは、平均的な牡蠣の15個分になるため、毎日15個以上食べなければ、亜鉛の過剰摂取にはなりません。
しかし、牡蠣には亜鉛以外の栄養素も含まれているため、亜鉛の過剰摂取にならなくても他の栄養素の耐容上限量になってしまうケースがあります。
例えば、牡蠣100g(5個分)には184mgのプリン体が含まれており、推奨摂取量は1日当たり400mg以下です。
これは牡蠣10個以下に相当します。
そのため、亜鉛の過剰摂取は15個以上食べなければ心配ありませんが、プリン体の過剰摂取のことを考えると、10個以下に抑えたほうがよいでしょう。
亜鉛を効率良く摂取する方法とは?
ここでは亜鉛不足でお困りの方に、効率良く摂取する方法を紹介します。
亜鉛の吸収効率を高めてくれる食材も一緒に摂取する
亜鉛には、ビタミンCやクエン酸など一緒に摂取すると吸収率を高めてくれる食材があります。
ビタミンCはアセロラなどの果実類に多く含まれており、クエン酸はレモンなどの柑橘類に多く含まれている栄養素です。
亜鉛を効率良く摂取したい方は、ビタミンCやクエン酸が含まれている食材も一緒に食べましょう。
また、カルシウムや食物繊維などの亜鉛の吸収を阻害する栄養素を控えることも、効率良く摂取するためには大切です。
サプリメントを利用する
サプリメントは、用法・用量を守っていれば過剰摂取することはありません。
また、亜鉛の吸収率を高めるビタミンCやクエン酸などが含まれている製品もあります。
気軽に亜鉛を摂取したい方には、サプリメントを利用することがおすすめです。

薄毛予防として気をつける生活習慣とは
亜鉛の摂取量だけではなく、以下の生活習慣を見直すことも薄毛予防には大切です。
・寝不足
・運動不足
・偏った食生活
・頭皮が不衛生
・喫煙
・過度のアルコールを摂取
・過度なストレスを感じる生活

生活習慣も薄毛の原因のひとつとされているため、上記に当てはまる方は改善するように努めましょう。
髪の毛に関する悩みを抱えている方はクリニックへの相談がおすすめ
亜鉛の推奨摂取量を守るだけでは、薄毛や抜け毛対策としては不十分です。
薄毛や抜け毛の原因はAGAだけではないため、原因を調べて適切な処置をする必要があります。
そのため、しっかりと育毛効果を実感したい方は、薄毛治療を行っているクリニックで医師の診療を受けることをおすすめします。
まとめ
亜鉛が髪の毛に及ぼす影響や過剰摂取が引き起こす可能性がある症状、推奨基準量、耐容上限量などについて紹介しました。
亜鉛は髪の毛の成長に必要な栄養素ですが、過剰に摂取すると薄毛や抜け毛を引き起こす可能性があるので注意しなければなりません。
プライベートスキンクリニックforMENは、ミノキシジル(濃度に段階あり)+フィナステリドもしくはデュタステリドの「オーダーメイド治療薬」や、「agaメソセラピー」によるAGA治療を主に行っております。
薄毛や抜け毛でお悩みの方は、当クリニックまでお気軽にご相談ください。
#亜鉛 #亜鉛摂りすぎ #はげる #薄毛 #AGA
よくあるご質問
Q.サプリメントを飲み忘れた次の日に2日分飲んでも問題ありませんか?
A.飲み忘れたからといって、まとめて飲んではいけません。
1日の用量を守るようにしましょう。
所在地 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル2階
TEL 06-6940-7101
FAX 06-6940-7102
受付時間 10:30〜19:00 (完全予約制)
この施術ページの監修医師
医療法人優聖会最高顧問井畑 峰紀
糸リフトやフィラー注入によるしわ・たるみ治療や、にきび治療などの美肌治療を中心とした美容医療に携わる、確かな実績を持つ医師。

糸リフトやフィラー注入によるしわ・たるみ治療や、にきび治療などの美肌治療を中心とした美容医療に携わる、確かな実績を持つ医師。
所属
- 平成15年
- 大阪医科大学 形成外科教室:入局
- 平成21年
- 大阪医科大学 助教(准):就任
美容クリニック非常勤勤務:歴任
- 平成24年
- 医学博士学位取得
日本形成外科学会 専門医認定
- 平成25年
- 某美容クリニック:院長就任
- 令和5年
- プライベートスキンクリニック
最高顧問:就任 現在に至る
略歴
- 一般社団法人日本形成外科学会 形成外科専門医
- 特定非営利活動法人日本レーザー医学会 認定医
- 一般社団法人国際抗老化再生医療学会 正会員
- 一般社団法人 日本美容外科学会 JSAPS(Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery) 正会員
- 一般社団法人日本美容皮膚科学会(Japanese Society of Aesthetic Dermatology 正会員
- 一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会 正会員
- アラガン社 VST(ボトックスビスタ)認定医
- アラガン社 ヒアルロン酸バイクロスシリーズ注入認定医
- Miramar Labs社(ミラドライ開発社)ミラドライ認定医